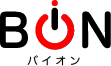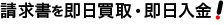債務不履行とか
債務不履行は、契約などで定められた義務を履行しないことを指します。ビジネスの現場では、さまざまな場面で債務不履行が発生する可能性があります。
例えば、A社が自社の製品を製造するために、B社から材料Cを仕入れる契約を結んだとしましょう。
A社側は購入したCを受け取る権利を有する一方で、その代金を支払う義務を負っています。言い換えれば、この取引を行った時点でCを受け取るという「債権」を得るとともに、その代金を支払うという「債務」が生じたことになります。
これに対し、B社はCを引き渡す義務が生じると同時に、その代金を受け取る権利を得ています。すなわち、B社にとってはCを引き渡すことが「債務」であり、その代金を受け取ることが「債権」に相当するわけです。
なお、その際に「債務」を果たさなかった理由は問われません。故意であるケースはもちろん、支払い期日を間違えていたような過失のケースであっても、「債務不履行」とみなされます。
ビジネスにおける債務不履行は、信用の失墜や取引関係の悪化につながりかねません。契約の重要性を認識し、責任を持って債務を果たすことが、健全なビジネス活動を営む上で不可欠です。
不渡りとの違い
不渡りとは、当座預金の残高不足によって支払い期日に手形や小切手が決済できないことを指します。手形と小切手は主に企業間取引における支払い手段です。金額や支払期日を記載して発行され、受け取った側は銀行で現金化することが可能です。
不渡りが発生すると、手形や小切手を受け取った側(受取人)はお金を受けれず、損失を被ることになります。振出人は銀行取引停止処分を受け、信用が大きく失われます。
不渡りは、手形や小切手の支払いができないことに焦点を当てた概念であるのに対し、債務不履行はより広範な義務の不履行を指します。
また、不渡りは支払不能の事実を示すのに対し、債務不履行は必ずしも支払不能を意味するわけではありません。
債務不履行の3つの種類
債務不履行は以下の3つの種類に分類されます。
・履行遅滞
・履行不能
・不完全不履行
履行遅滞
履行遅滞とは、債務の履行が可能であったにもかかわらず、約束の期日に遅れてしまうことです。商品の納入や代金の支払いが遅れるケースが該当します。
履行不能
履行不能は、債務の履行が不可能となってしまった状態です。例えば、売買契約において、販売予定の商品が災害により滅失した場合や、輸入禁止措置により商品の調達が不可能になった場合などが該当します。
ただし、お金の支払いや返済に関する「金銭債務」については履行不能とみなされることがなく、債務者が代金を持ち合わせていないケースであっても「履行遅延」として扱われます。
不完全不履行
不完全不履行は、「債務」の一部を履行したものの、残りは履行していないというパターンです。運送会社に配送を依頼したところ、輸送中の不備で到着した時点で荷物が破損していたケースがその一例です。
不完全不履行においても、金銭債務については対象外となります。たとえば、借入金の一部を返済したものの、残債の支払いが滞っているという場合は、不完全不履行ではなく、履行遅滞」とみなされます。
債務不履行が発生した際の3つの対抗手段
債務不履行が発生すると、債権者は不利益を被ることになります。当然債務者が債権を履行しない場合、債権者側は以下のような対抗手段を取ることが可能です。
・契約解除
・損害賠償請求
・強制執行
契約解除
契約解除では、一方の当事者が契約上の義務を履行しない場合、相手方は契約を解除することができます。
契約は社会的な約束事であり、法的な拘束力もあることから、通常は容易に解除できません。しかしながら、「債務不履行」となった場合、いずれかに該当すれば、契約解除が可能となります。
・当事者同士が合意している
・契約書において解除に関する定めが記載されている
・民法の規定に合致している
契約解除するためには事前に相手方に催促し、期間を定めて履行を求める必要があります。それでも履行がない場合、または履行が不可能な場合に、契約解除の意思表示を行うことが可能です。
損害賠償請求
損害賠償請求は、契約違反や違法行為などによって受けた被害に相当する金銭の支払いを、その原因をもたらした相手に求めることです。債権者は「債務」を履行しない相手に対し、実際の損害分を請求できます。
強制執行
強制執行は、債権者が裁判で債務者を訴えて勝訴したにもかかわらず、それでも「債務」が履行されない場合の最終手段です。国が債務者の財産を差し押えるという手続きを行い、「債権」の回収を図ります。
まとめ:債務不履行を避けるためにも対策が肝心!
「債務」という自らの義務を果たさない「債務不履行」と、当座預金の残高が足りなくて手形や小切手を受け取った側が現金化できない「不渡り」は、どちらもビジネスを営むうえで極力避けたいタブー。
支払いに困ってそのような事態に陥る前に計画的な資金調達を進めるのが賢明です。「売掛債権」を即日現金化することも可能なファクタリングなどを上手に活用し、どうにかして窮地を脱したいところです。
オンライン完結だから早い!バイオンのAIファクタリング
最短60分のAI審査で、請求書(売掛金)を即日買取させていただきます。
個人事業主様から中小企業様まで資金調達の際はぜひバイオンのAIファクタリングサービスをご利用ください。
▶︎ 登録がお済みでない方はコチラ!